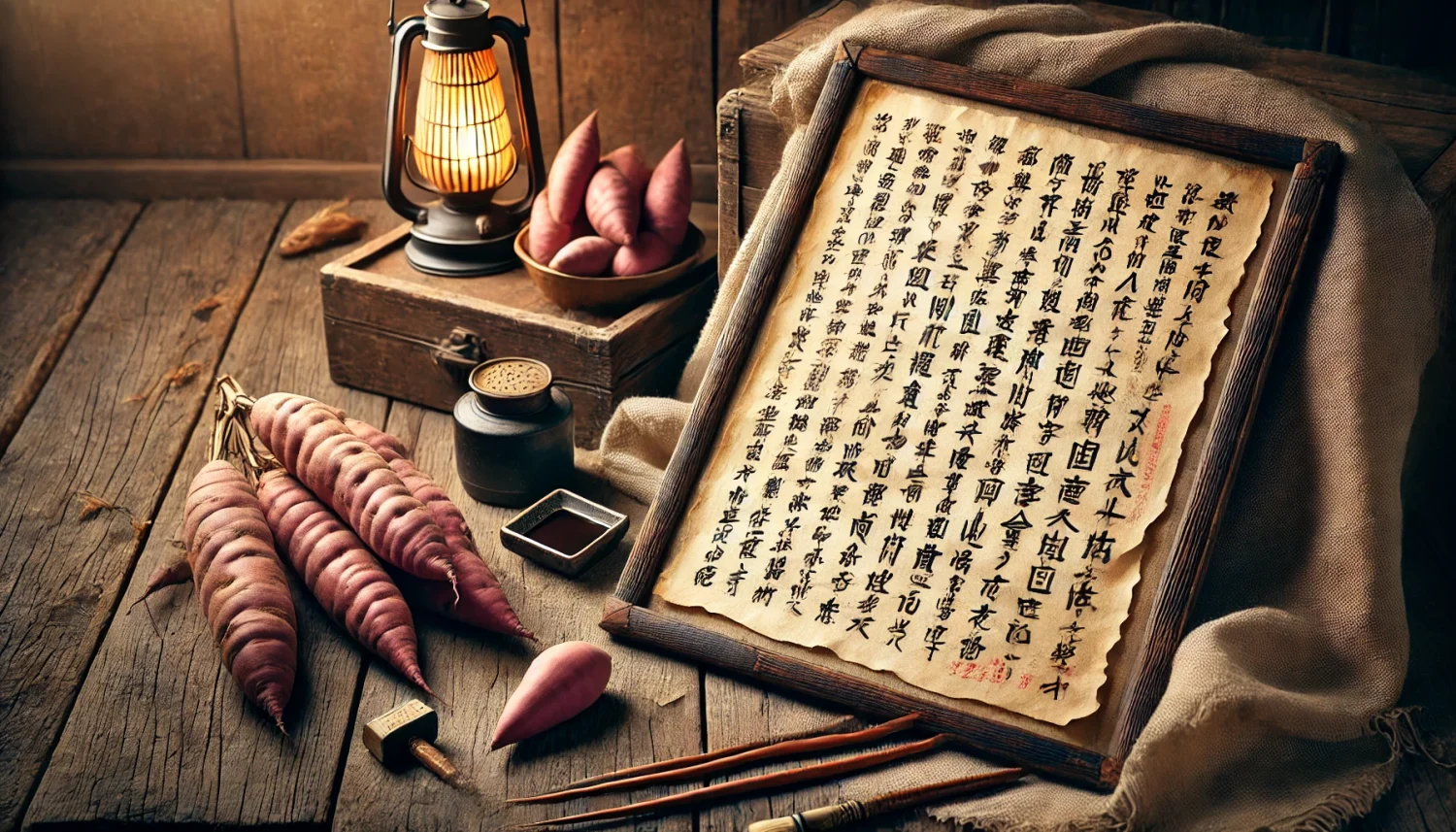秋の食卓に欠かせないさつまいも。実は多くの別名があり、その背景には壮大な歴史が隠されています。この記事では、そもそもさつまいもの起源と伝来ルートを解説することから始め、なぜ薩摩なのか?さつまいもの由来を明らかにします。
さらに、さつまいもの別名と名前の由来を個別に解説する中で、甘藷(かんしょ)の意味と由来とは何か、唐いも(からいも)はどこから来た?という疑問や、琉球いもやその他の呼び名を紹介していきます。
また、十三里って何?江戸の粋なネミングに隠された話など、さつまいもの別名に隠された名前の由来と歴史を紐解き、地域で異なる呼び方の理由を深掘りします。
品種名で呼ぶ現代のさつまいも事情や、さつまいも関連の記念日やイベントにも触れ、最後に総括!さつまいもの別名と名前の由来をまとめます。
- さつまいもの様々な別名とその意味がわかる
- 呼び名の背景にある歴史的な流れを理解できる
- 地域による呼び方の違いがなぜ生まれたかわかる
- 誰かに話したくなるさつまいもの雑学が身につく
さつまいもの別名と名前の由来を個別に解説
さつまいもの起源と伝来ルートを解説

私たちの食卓で親しまれているさつまいもですが、その故郷は遠く離れたメキシコ周辺の熱帯アメリカです。紀元前から栽培されていた記録があり、古代文明を支えた重要な作物の一つでした。
このさつまいもが世界中に広まるきっかけとなったのが、15世紀末からの大航海時代です。コロンブスによってヨーロッパに紹介された後、船乗りたちの貴重な食料として世界中の港へと運ばれていきました。
日本へは、ヨーロッパから直接ではなく、アジアを経由する壮大な旅を経て到着します。その主要な伝来ルートは以下の通りです。
【さつまいもの伝来ルート】
熱帯アメリカ → フィリピン → 中国・福建省(1594年頃) → 琉球王国(現在の沖縄県・1604年) → 薩摩藩(現在の鹿児島県・1705年頃) → 江戸(全国へ)
中国へは、福建省出身の商人であった陳振竜(ちんしんりゅう)が、当時スペイン領だったフィリピンから密かに持ち帰ったと伝えられています。飢饉に苦しむ故郷の人々を救いたいという強い思いがあったのです。
そして、琉球、薩摩へと伝わり、日本全国へと普及していきました。この長い旅路こそが、さつまいもに多くの別名をもたらした最大の要因となっています。
なぜ薩摩なのか?さつまいもの由来

さつまいもを漢字で表記すると「薩摩芋」。これは最も広く知られている名称であり、言葉の通り「薩摩国(現在の鹿児島県)から日本全国へ広まった芋」という意味がその由来です。
1705年、琉球を訪れた薩摩の船乗り、前田利右衛門(まえだりえもん)がさつまいもを故郷の指宿市山川に持ち帰り、栽培を試みたのが本格的な始まりとされています。
さつまいもは、鹿児島の火山灰性で痩せたシラス台地でもよく育ち、台風や干ばつにも強いという特性を持っていました。このため、食糧難に悩む薩摩藩にとってまさに救世主のような作物だったのです。
特に、1732年に西日本を襲った「享保の大飢饉」では、米が凶作となる中でさつまいもが多くの人々の命を救いました。この実績によって、さつまいもの価値は不動のものとなり、救荒作物として全国から注目を集めるようになります。
そして、栽培の拠点であった「薩摩」の名前を冠して、「薩摩芋」として日本中に広まっていったのです。前田利右衛門は、その功績から地元で「からいもどん(さつまいもの神様)」として今も敬われています(参考:農林水産省:サツマイモの伝来-前田利右衛門と青木昆陽-)。
甘藷(かんしょ)の意味と由来とは

さつまいもの別名として、「薩摩芋」と並んで重要なのが「甘藷(かんしょ)」という呼び名です。これは、さつまいもの中国での名称(漢名)がそのまま日本に伝わったものです。
「甘」は甘い、「藷」は芋類を意味する漢字であり、その名の通り「甘い芋」という意味を持っています。味わいを素直に表現した、非常に分かりやすい名前です。
日本でも江戸時代から広く使われており、現代においてもその重要性は変わりません。農林水産省が発表する作物統計調査など、公的な統計や学術論文では、今でも「さつまいも」ではなく「かんしょ」が正式名称として用いられています。
豆知識:『蕃藷考』と甘藷先生
江戸幕府8代将軍・徳川吉宗の時代、蘭学者であった青木昆陽(あおきこんよう)は、さつまいもの救荒作物としての有用性を説いた専門書『蕃藷考(ばんしょこう)』を著しました。
これが幕府に認められ、関東一円でのさつまいも栽培が試みられるきっかけとなります。彼の多大な功績により、人々は敬意と親しみを込めて「甘藷先生」と呼ぶようになりました(参考:農林水産省:サツマイモの伝来-前田利右衛門と青木昆陽-)。
日常生活で「かんしょ」と呼ぶ機会は少ないかもしれませんが、日本の農業や歴史を語る上では欠かせない、由緒ある正式名称なのです。
唐いも(からいも)はどこから来た?
九州地方、特にさつまいもの一大産地である鹿児島県や宮崎県では、今でも日常的に「唐いも(からいも)」という呼び名が使われています。地元のお土産品や焼酎の原料表示などでも、この名称を目にすることができます。
この「唐(から)」とは、当時の日本にとって海外、特に中国を指す言葉でした。つまり、「唐いも」とは「中国から伝来した芋」という意味になります。
前述の伝来ルートを見ても分かる通り、さつまいもは中国から琉球を経由して日本本土へともたらされました。そのため、伝来のルーツである中国(唐)を意識して、この名が付けられたと考えられています。
「この芋はどこから来たのか?」
「唐から来たらしいですよ」
このような会話が、そのまま呼び名として定着したのかもしれません。関東以北の人々が「薩摩から来た芋」と認識したのに対し、伝来の玄関口に近かった九州の人々は「(ルーツである)唐から来た芋」と認識していた、という地理的な視点の違いが表れていて非常に興味深いですね。
琉球いもやその他の呼び名を紹介

さつまいもの伝来史を語る上で欠かせないのが、中継地点となった沖縄、すなわち琉球王国の存在です。その名残を示す呼び名が「琉球いも(りゅうきゅういも)」です。
これは主に、琉球から直接さつまいもが伝わった薩摩藩での古い呼び名です。薩摩の人々から見れば、この新しい作物は紛れもなく「琉球からやって来た芋」でした。後に「薩摩芋」という呼び名が全国区になりますが、伝来当初の歴史を物語る貴重な別名と言えるでしょう。
その他にも、さつまいもには地域や時代を反映した様々な呼び名が存在します。
| 別名 | 読み方 | 由来・概要 |
|---|---|---|
| 蕃藷 | ばんしょ | 「蕃」は外国や異民族を意味する言葉で、「外国から来た芋」を指す古い呼び名です。青木昆陽の著書『蕃藷考』のタイトルにも使われています。 |
| 孝行いも | こうこういも | 痩せた土地でもよく育ち、農家(親)の暮らしを助ける「親孝行な作物」であることから、長崎県の対馬地方などで呼ばれるようになったと言われています。 |
| アメリカいも | あめりかいも | これは比較的新しい呼び名で、明治時代にアメリカから新たな品種が導入された際に、区別するために一部地域で使われるようになりました。 |
これらの呼び名一つひとつに、さつまいもと日本の各地域の人々との深いつながりが刻まれています。
十三里って何?江戸の粋なネミング

さつまいもの数ある別名の中でも、ひときわ異彩を放ち、江戸っ子の遊び心が感じられるのが「十三里(じゅうさんり)」という呼び名です。
江戸時代、焼き芋は冬の江戸庶民にとって手軽で美味しい甘味として大ブームになりました。そんな中、ある焼き芋屋がライバルと差をつけるために、こんなキャッチコピーを掲げたと言われています。
「栗(九里)より(四里)うまい十三里」
当時、甘くて美味しいものの代表格は「栗」でした。その栗の美味しさを「九里」という単位に置き換え、「それ(九里)よりも(四里)美味しい」という洒落を効かせたのです。この計算式がこちらです。
栗(9里)+ より(4里)= 13里
この粋なネーミングが江戸庶民の心を見事に捉え、「焼き芋=十三里」という呼び名が瞬く間に広まりました。さらに、この説を補強するように、さつまいもの名産地として知られた小江戸・川越(現在の埼玉県川越市)が、江戸の中心地である日本橋からおよそ十三里(約52km)の距離にあったことも、この呼び名が定着する後押しになったと言われています。単なる語呂合わせだけでなく、地理的な事実も背景にあったのです。
さつまいもの別名に隠された名前の由来と歴史
地域で異なる呼び方の理由を深掘り

ここまで見てきたように、さつまいもには実に多くの呼び名が存在します。なぜ一つの作物にこれほど多様な名前が付けられたのでしょうか。その核心的な理由は、繰り返しになりますが、さつまいもの「伝来ルート」と、各地域の人々がそれを「どこから来たもの」と認識したかの違いにあります。
情報の伝わり方をイメージすると、この現象がよく理解できます。
それぞれの視点から見た「さつまいも」
- 琉球(沖縄)の視点:中国(唐)から来た最新の作物だ → だから「唐いも」と呼ぼう。
- 薩摩(鹿児島)の視点:隣の琉球から伝わってきた珍しい芋だ → だから「琉球いも」と呼ぼう。
- 江戸(東京)の視点:遠い薩摩藩で評判の、飢饉にも強い芋らしい → だから「薩摩芋」と呼ぼう。
このように、情報が人から人へ、地域から地域へと伝わる過程で、それぞれの場所での認識が呼び名として固定化されていったのです。これは、方言が生まれるプロセスにも似ています。
最終的に、政治経済の中心地であった江戸から全国へ広まった「薩摩芋」という呼び名が最も一般的になりましたが、伝来の経路上にあった地域では、今なお歴史的な名称が大切に受け継がれているのです。
品種名で呼ぶ現代のさつまいも事情
江戸時代から続く豊かな呼び名の文化を持つさつまいもですが、その呼ばれ方は現代において新たなステージに入っています。近年、スーパーや直売所では「さつまいも」という大きな括りではなく、「紅はるか」「安納芋」「シルクスイート」「鳴門金時」といった、具体的な品種名で呼ばれることが当たり前になりました(参考:指宿市公式サイト::さつまいも)。
これは、長年にわたる品種改良の賜物です。特に、農研機構(NARO)などの研究機関の努力により、食感や甘さ、見た目が異なる、個性豊かな品種が次々と開発されました。その結果、消費者は自分の好みに合わせて品種を選べるようになり、呼び方もより具体的になったのです。
「今日はねっとり甘い紅はるかで焼き芋にしようかな?」「それとも、上品な甘さのシルクスイートでスイーツ作りもいいわね!」
このように、現代の私たちは品種ごとの個性を楽しみ、その名前で語り合っています。これは、さつまいもの歴史に新たな1ページを刻む、現代ならではの文化と言えるでしょう。
| 品種名 | 食感タイプ | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 紅はるか | ねっとり系 | 非常に糖度が高く、加熱すると蜜が出るほど。しっとりなめらかな食感が人気。 |
| 安納芋 | ねっとり系 | 種子島特産。水分が多く、焼くとクリームのようにねっとりとした食感になる。濃厚な甘さが特徴。 |
| シルクスイート | しっとり系 | その名の通り、絹のようになめらかな舌触り。上品な甘さでスイーツ作りにも向いている。 |
| 鳴門金時 | ホクホク系 | 徳島県特産。栗のようなホクホクとした食感と、昔ながらの素朴な甘さが特徴。天ぷらなどにも最適。 |
さつまいも関連の記念日やイベント

さつまいもが日本文化に深く根付いている証として、関連する記念日の存在も挙げられます。江戸時代の粋な別名「十三里」にちなみ、毎年10月13日は「さつまいもの日」に制定されています。
この記念日は、1987年(昭和62年)に、さつまいもの名産地である埼玉県川越市の生産者や愛好家らでつくる「川越いも友の会」によって制定されました(参考:川越市:川越とサツマイモ)。「十三里」という歴史的な呼び名を後世に伝えたいという思いが込められています。
また、10月はさつまいもの収穫が最盛期を迎え、まさに旬の美味しさを味わえる時期でもあります。
【さつまいもの日】
日付:毎年10月13日
由来:さつまいもの別名「十三里(じゅうさんり)」から。
制定者:川越いも友の会(1987年)
この日には、全国各地でさつまいも掘り体験やフェアなどのイベントが開催されることも多く、秋の訪れを感じさせてくれます。次に10月13日を迎える際には、さつまいもの名前に隠された江戸っ子のユーモアに思いを馳せながら、旬の味覚を楽しんでみてはいかがでしょうか。
総括!さつまいもの別名と名前の由来

この記事では、さつまいもの様々な別名と、その背景にある壮大な歴史や文化について詳しく解説してきました。最後に、この記事の重要なポイントをリスト形式で振り返ります。
- さつまいもの原産地はメキシコを中心とする熱帯アメリカである
- 日本へは中国から琉球、そして薩摩へと長い旅を経て伝わった
- 「さつまいも」の由来は栽培拠点であった薩摩から全国へ広まったため
- 「甘藷(かんしょ)」は中国での呼び名に由来し現在も公的な正式名称である
- 「唐いも(からいも)」は中国(唐)から来た芋という意味で九州で使われる
- 「琉球いも」は琉球から伝わったことが由来で薩摩での古い呼び名である
- 別名が数多く存在する最大の理由は伝来ルートがそのまま呼び名になったから
- 地域によって呼び方が違うのはどこから伝わったかという認識の違いによる
- 「十三里」は江戸の焼き芋屋が考案した洒落が元になった粋な呼び名である
- 「栗(九里)より(四里)うまい」という意味がこの名前に込められている
- 名産地・川越が江戸から約十三里の距離だったことも由来の一つとされる
- 蕃藷や孝行いもなどその土地の歴史を反映した呼び名も存在する
- 現代では紅はるかなど具体的な品種名で呼ばれることが一般的になっている
- 毎年10月13日はさつまいもの日として記念日に制定されている
- この記念日の由来は江戸時代の別名である十三里から来ている