秋の味覚としておなじみのさつまいも。その甘さと食感で多くの人に愛されていますが、「さつまいもは何科の植物?」と聞かれると、意外と知らない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、さつまいもは何科?ヒルガオ科の仲間を解説というテーマで、その正体に迫ります。実は、さつまいもはヒルガオ科でアサガオの仲間であり、一方でじゃがいもはトマトと同じナス科の野菜なのです。
主要なイモ類の分類を一覧で比較しながら、意外な仲間である空心菜も同じヒルガオ科であることや、農林水産省による野菜の分類とは何かについても触れていきます。
「さつまいもは何科」から学ぶ植物の知識として、塊根と塊茎の違いは食べる部位にあること、さつまいもの名前の由来は薩摩から来ている歴史、その原産地と日本への伝来、そしてさつまいもの花が咲くのは珍しいのか、といった疑問まで深掘りします。
この記事を読めば、総括としてさつまいもは何科かの疑問を解決できるでしょう。
- さつまいもの正しい植物分類
- じゃがいもなど他のイモ類との明確な違い
- 食べている部位や名前の由来に関する豆知識
- さつまいもの花や歴史についての面白い事実
さつまいもは何科?ヒルガオ科の仲間を解説
- さつまいもはヒルガオ科でアサガオの仲間
- じゃがいもはトマトと同じナス科の野菜
- 主要なイモ類の分類を一覧で比較
- 意外な仲間、空心菜も同じヒルガオ科
- 農林水産省による野菜の分類とは
さつまいもはヒルガオ科でアサガオの仲間

結論から言うと、さつまいもは「ヒルガオ科」の植物です。ヒルガオ科と聞くと、夏に美しい花を咲かせるアサガオやヒルガオを思い浮かべる方が多いかもしれません。実は、さつまいもはまさしく、あのアサガオと非常に近い親戚関係にあるのです。
植物の分類は、主に花や葉、茎の形といった特徴に基づいて行われます。さつまいもの花は、アサガオの花を少し小さくしたような、淡いピンク色や紫色をしたラッパ状の形をしています。この花の形が、ヒルガオ科に分類される決定的な理由の一つです。
普段私たちが食べているのは根の部分なので、なかなか花のイメージは湧きにくいかもしれません。しかし、植物学的には、夏を彩るアサガオと同じグループに属していると知ると、さつまいもへの見方が少し変わって面白いですね。
豆知識:学名について
さつまいもの学名は「Ipomoea batatas」といいます。この「Ipomoea(イポメア)」が、アサガオなどが含まれるサツマイモ属を指す言葉です。
じゃがいもはトマトと同じナス科の野菜

さつまいもとしばしば比較される「じゃがいも」ですが、こちらは全く異なる科に属しています。じゃがいもは、トマトやナス、ピーマンなどと同じ「ナス科」の植物なのです。食感や調理法が似ているため混同されがちですが、植物としての系統は全く異なります。
この事実は、やはり花を見るとよく理解できます。じゃがいもの花は、星のような形で、色や形がナスの花とそっくりです。畑で両方の花を見比べる機会があれば、その類似性に驚くことでしょう。
「イモ」という名前で一括りにされがちですが、さつまいもとじゃがいもは、いわば植物界の赤の他人。料理で使い分けるように、植物としての違いも知っておくと面白いですよ。
このように、見た目や用途が似ていても、植物学的な分類は全く違うという例はたくさんあります。野菜売り場で、じゃがいもを見たら「これはトマトの仲間なんだな」と思い出してみるのも一興です。
主要なイモ類の分類を一覧で比較
「イモ」と呼ばれる野菜はたくさんありますが、そのほとんどは異なる科に属しています。ここで、私たちの食卓によく登場する主要なイモ類が、それぞれ何科に分類されるのかを一覧表で見てみましょう。
| イモの種類 | 科 | 主な仲間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| さつまいも | ヒルガオ科 | アサガオ、ヒルガオ、空心菜 | 食べているのは「塊根(かいこん)」 |
| じゃがいも | ナス科 | トマト、ナス、ピーマン、唐辛子 | 食べているのは「塊茎(かいけい)」 |
| 里芋(さといも) | サトイモ科 | こんにゃく芋、カラー(観葉植物) | 食べているのは「塊茎(かいけい)」 |
| 山芋・長芋 | ヤマノイモ科 | 自然薯(じねんじょ) | 食べているのは「塊根(かいこん)」 |
| こんにゃく芋 | サトイモ科 | 里芋、タロイモ | 食べているのは「球茎(きゅうけい)」 |
このように、「〇〇イモ科」という分類は存在せず、それぞれが独自の科に属していることが分かります。特に、さつまいもとじゃがいもは科が違うだけでなく、私たちが食べている部位の成り立ちも異なる、非常に興味深い関係です(参考:農林水産省:いも・でん粉に関する資料)。
意外な仲間、空心菜も同じヒルガオ科

さつまいもがヒルガオ科であることはご紹介しましたが、実は野菜の中にもう一つ、同じ科に属する身近なものが存在します。それは、中華料理などで人気の葉物野菜「空心菜(クウシンサイ)」です。
空心菜は、その名の通り茎の中が空洞になっているのが特徴で、シャキシャキとした食感が美味しい野菜です。さつまいもが根を食べるのに対し、空心菜は葉と茎を食べるため、同じ仲間だとはなかなか想像がつきにくいかもしれません。
しかし、空心菜もさつまいもと同様に、アサガオに似た白や薄ピンク色の花を咲かせます。繁殖力が非常に旺盛で、温暖な地域ではつるを伸ばしてどんどん広がっていく点も、ヒルガオ科の植物に共通する特徴と言えるでしょう。
甘いさつまいもと、炒め物で活躍する空心菜が親戚だと思うと、植物の世界の奥深さを感じますね。
農林水産省による野菜の分類とは
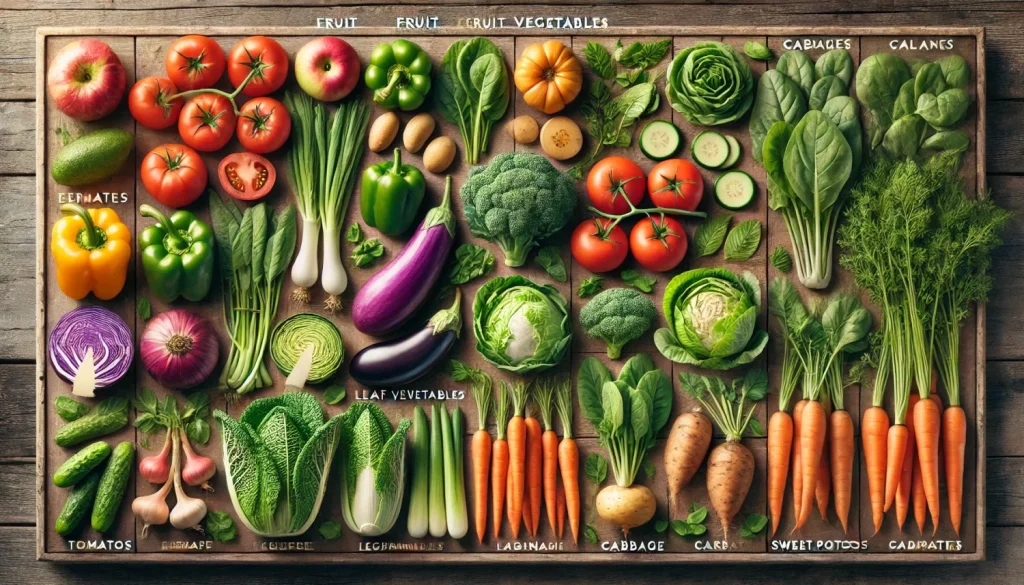
これまで解説してきた「〇〇科」という分類は、植物の花や葉の形などに基づいた「植物学上の分類」です。一方で、農林水産省などが用いる分類は、私たちが利用する部分(可食部)や栽培方法に基づいた「園芸学上の分類」が一般的です。
この園芸学上の分類では、野菜は以下のように分けられます。
- 果菜類:果実を食べる野菜(トマト、きゅうり、ナスなど)
- 葉茎菜類:葉や茎を食べる野菜(キャベツ、ほうれん草、アスパラガスなど)
- 根菜類:根の部分を食べる野菜(大根、にんじん、ごぼうなど)
この分類に従うと、さつまいもは根が肥大した部分を食べるため、「根菜類」に分類されます。
分類の視点の違いに注意
植物学上の分類(ヒルガオ科)と、園芸学上の分類(根菜類)は、全く異なる視点からのグループ分けです。どちらが正しいというものではなく、目的によって使い分けられています(参考:農林水産省:野菜の分類について教えてください。)。例えば、連作障害を避けるためには植物学上の「科」を意識することが重要です。
「さつまいもは何科」から学ぶ植物の知識
- 塊根と塊茎の違いは食べる部位にある
- さつまいもの名前の由来は薩摩から
- さつまいもの原産地と日本への伝来
- さつまいもの花が咲くのは珍しい?
- 総括:さつまいもは何科かの疑問を解決
塊根と塊茎の違いは食べる部位にある

さつまいもとじゃがいもの大きな違いの一つに、私たちが食べている部位の成り立ちが挙げられます。さつまいもは「塊根(かいこん)」、じゃがいもは「塊茎(かいけい)」と呼ばれる部分を食べています。
言葉は似ていますが、この二つは全くの別物です。
塊根(かいこん)とは
塊根は、植物の「根」の一部が、養分を蓄えて肥大化したものです。さつまいもをよく見ると、ひげ根が生えているのが分かりますが、これは根であることの証拠です。大根やにんじんも、同じく根が肥大した「主根」という部分を食べており、塊根の仲間に分類できます。
塊茎(かいけい)とは
一方、塊茎は、植物の「茎」の一部が、地中で養分を蓄えて肥大したものです。じゃがいもの表面にある「くぼみ」は「芽」であり、ここから新しい茎や葉が伸びていきます。これは茎が持つ特徴です。里芋もこの塊茎に分類されます。
見分け方のポイント
- さつまいも(塊根):ひげ根がある。芽は不定(どこから出るか決まっていない)。
- じゃがいも(塊茎):芽(くぼみ)がある。地上の茎と同じ構造を持つ。
このように、土の中にできるという点は同じでも、その正体が「根」なのか「茎」なのかという根本的な違いがあるのです(参考:日本植物生理学会:みんなのひろば「根茎と塊茎の違い」)。
さつまいもの名前の由来は薩摩から

「さつまいも」という名前は、その伝来の歴史に深く関係しています。この名前は、「薩摩の国(現在の鹿児島県)から広まった芋」であることに由来します。
17世紀初頭、さつまいもは中国から琉球王国(現在の沖縄県)に伝わりました。その後、1705年に薩摩藩主の島津吉貴が、琉球から苗を取り寄せて栽培を試み、領内での栽培に成功します。
当時の薩摩藩は、台風や干ばつによる食糧難にたびたび見舞われていました。しかし、痩せた土地でも育ちやすく、災害にも強いさつまいもは、まさに救荒作物として領民を飢饉から救う存在となりました。ここから、薩摩藩はさつまいもの栽培を奨励し、その栽培技術は全国へと広まっていきました。
このような背景から、「薩摩から来た芋」という意味で「薩摩芋(さつまいも)」と呼ばれるようになったのです。地域によっては「唐芋(からいも)」や「琉球芋(りゅうきゅういも)」と呼ばれることもあり、それぞれが伝来の歴史を物語っています。
さつまいもの原産地と日本への伝来

さつまいもの名前の由来は薩摩ですが、そのルーツをさらに遡ると、原産地は中南米の熱帯地域だと考えられています。メキシコ中央部からペルーにかけての広大な地域で、紀元前8000年~6000年頃にはすでに栽培が始まっていたとされる、非常に歴史の古い作物です。
その後、大航海時代にコロンブスによってヨーロッパに持ち帰られ、そこから世界中へと広まっていきました。アジアへは、スペインやポルトガルを通じてフィリピンや中国に伝わったとされています。
日本への伝来ルートは、主に以下の2つが知られています。
日本への伝来ルート
- 中国 → 琉球 → 薩摩 → 全国:これが最も主要なルートで、「さつまいも」の語源となりました。
- 東南アジア → 長崎・対馬:別のルートで九州の一部にも伝わったとされています。
特に、江戸時代中期に蘭学者の青木昆陽がさつまいもの栽培を研究し、その有用性を徳川吉宗に説いたことで、関東地方でも栽培が奨励されました。これにより、享保の大飢饉の際に多くの人々を救ったことから、青木昆陽は「甘藷先生(かんしょせんせい)」と称えられています(参考:農林水産省:サツマイモはどこからきたの?)。
さつまいもの花が咲くのは珍しい?

さつまいもがアサガオに似た美しい花を咲かせることは前述の通りですが、実際に日本でその花を見る機会はほとんどありません。なぜなら、さつまいもは特定の条件下でないと花を咲かせにくい性質を持っているからです。
さつまいもは「短日植物(たんじつしょくぶつ)」に分類されます。これは、1日の日照時間が一定の時間よりも短くならないと、花を咲かせるための芽(花芽)が作られないという性質です。
さつまいもの原産地である中南米の熱帯地域は、年間を通じて日照時間が比較的短い地域です。そのため、日本の夏のように日照時間が長い環境では、花を咲かせるためのスイッチが入らないのです。
ただし、全く咲かないわけではありません。品種や気候条件によっては、秋になり日照時間が短くなってきた頃に花が咲くことがあります。特に、気候が温暖な沖縄や九州南部では、本土に比べて開花する様子が観察されやすいと言われています。
もし家庭菜園などでさつまいもの花が咲いたら、それは非常に珍しく、幸運なことかもしれませんね。
総括:さつまいもは何科かの疑問を解決
この記事では、「さつまいもは何科?」という疑問を起点に、その分類から歴史、豆知識までを詳しく解説しました。最後に、本記事の要点をリスト形式でまとめます。
- さつまいもはヒルガオ科の植物
- 身近な仲間にはアサガオや空心菜がある
- じゃがいもはナス科でトマトやピーマンの仲間
- 里芋はサトイモ科、山芋はヤマノイモ科に属する
- 「イモ科」という植物の分類は存在しない
- 農林水産省の分類では根菜類に分けられる
- 私たちが食べているのは根が肥大した塊根
- じゃがいもは茎が肥大した塊茎を食べる
- 塊根と塊茎は成り立ちが全く異なる
- 名前の由来は薩摩から全国へ広まった歴史から
- 原産地は中南米の熱帯地域
- 大航海時代を経て世界中に広まった
- 日本へは主に琉球経由で伝来した
- さつまいもの花はアサガオに似ている
- 日照時間が短い条件で開花する短日植物
- 日本の夏は日照時間が長いため花が咲きにくい

